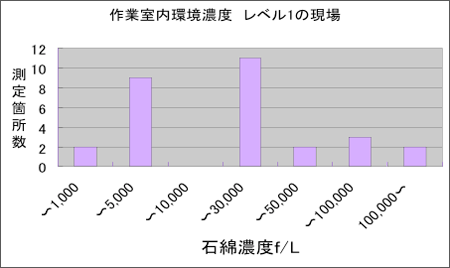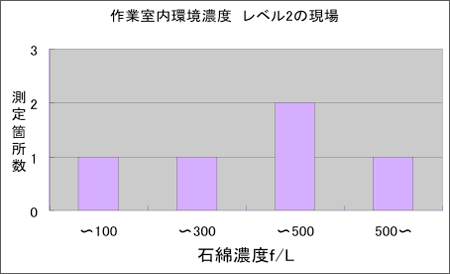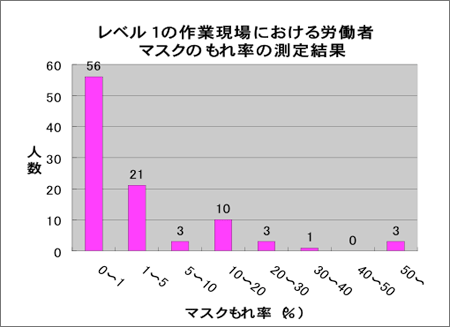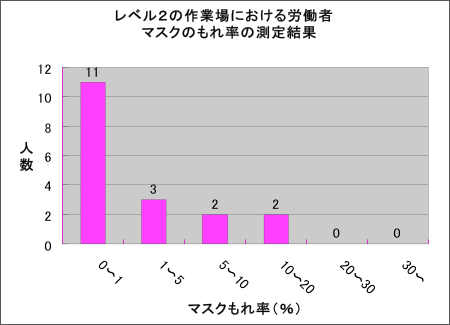| 2008年度の研究を基に作成された情報です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石綿による肺がん、中皮腫等の健康障害が発生するおそれがあるため、従来から、労働安全衛生法や特定化学物質等障害予防規則等に基づく規制が行われてきており、平成7年のアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)含有製品の製造等の禁止、さらに平成16年10月のクリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤の製造等の禁止等により、国内の石綿使用量が削減されてきましたが、今後、石綿が建材として使用されている建築物の解体が増加し、そのピークは2020年から2040年頃と想定されています。 ○ 健康診断の対象者
○ 健康診断の実施時期
○ 健康診断の項目
○ 健康診断結果の報告・記録
○ マスク効率
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||